図1)国民医療費の推移
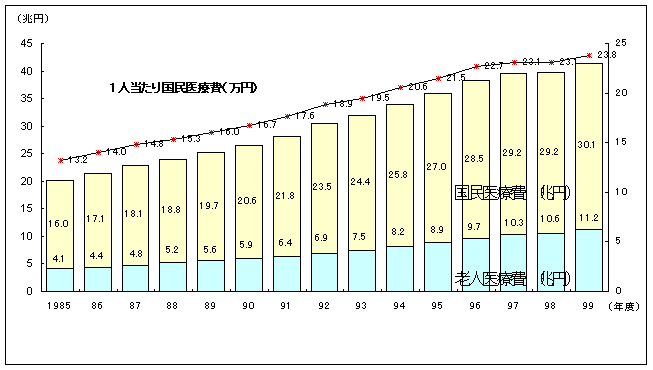
表1)対前年伸び率
1) 国民医療費
2) 医療保険制度の現状
3) 病院運営実態分析調査
4) 医療制度改革の動向
5) DRG/PPSの支払方式の試行状況
6) 2000年の診療報酬改訂の概要
7) 第4次医療法改正
8) 健康保険法一部改正内容
我が国の国民医療費は年々増え続け、平成11年には30兆円(推計)を超え、国民所得の伸び率が極めて低い水準にあるにもかかわらず、国民医療費も老人医療費も伸びており、国民所得に占める医療費の割合が増大している。
図1)国民医療費の推移
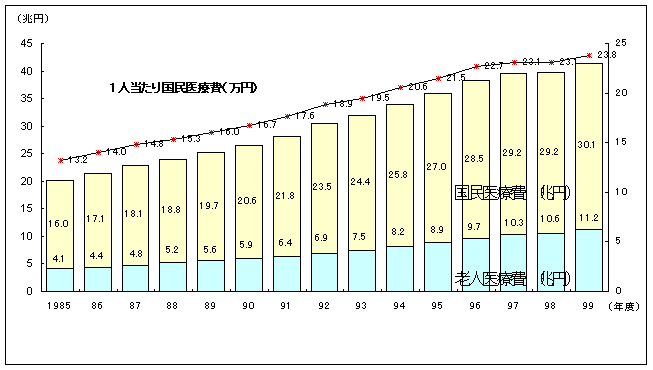
表1)対前年伸び率
| 89年度 (平成元) | 90 (2) |
91 (3) |
92 (4) |
93 (5) |
94 (6) |
95 (7) |
96 (8) |
97 (実績見込) (9) |
98 (見込) (10) |
99 (見込) (11) |
|
| 国民医療費 | 5.2 | 4.5 | 5.9 | 7.6 | 3.8 | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 2.2 | 0.2 | 3.0 |
| 老人医療費 | 7.7 | 6.6 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 5.7 | 2.7 | 6.2 |
| 国民所得 | 6.9 | 7.3 | 5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | -0.2 | -2.4 | 0.1 |
注) 1.
老人医療費の下の%は老人医療費の国民医療費に対する割合である。
注) 2.
平成9年度は実績見込、平成10年度、平成11年度は見込である。そのためこれらに係わる 諸率は今後変わる場合がある。
Data:平成11年度厚生白書 P437
不況により保険料収入が伸び悩む中で、保険給付費(医療費・薬剤費)の増加と老人医療費のための拠出(老人保健拠出金)が重荷となり、財政が窮迫する組合が増えてきた。
平成11年度の保険料収入に占める老人保健拠出金の割合は32.72%で、対前年3.29%の伸びである。
健康保険組合の保険料率の上限は、標準報酬(給与)の9.5%。これを事業主が約6%、披保険者が約3.5%という割合で案分してきた。平成11年度の平均保険料率は8.509%で対前年度0.023%上昇している。政管健保の保険料率(8.5%)以上の組合は、全国に約1800ある健保組合のうち997組合である。(全組合の55.8%)。平成11年度の赤字組合の割合は、84.6%で、対前年の14.2%の増加である。
政管健保では、健保組合では実施していなかった賞与からの保険料支払いがあるが、標準報酬に対する保険料率は8.5%に低下。これを事業主と披保険者がともに4.25%ずつ負担する決まりである。
厚生省としても「手を尽くしても存続が難しい組合が出てきており、やむを得ないところは自主解散を認めていく」方針に転換した。関係者の試算によると、健保組合のうち300近い組合が自主解散してもおかしくない財政窮迫状態にあるという。
平成11年度健保組合の収支予算の見込みは、3,969億円の赤字。平成6年度から6年連続の赤字となる見込み。赤字額は過去最高に達している。
表1)健保組合の経常収支トレンド
(億円)
| 経常収入 | 経常支出 | 収支差 | 赤字総額 | |
| 1995 | 55064 | 56286 | -1222 | 2062 |
| 1996 | 56256 | 58232 | -1976 | 2615 |
| 1997 | 59224 | 59241 | -17 | 1590 |
| 1998(予算) | 60207 | 61544 | -1337 | 2298 |
| 1999(予算) | 59441 | 63410 | -3969 | 4329 |
図1)赤字組合数
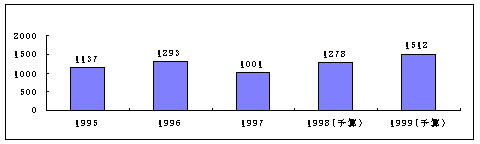
Data:健康保険組合連合会ホームページ
表2)平成10〜12年度の政管健保財政収支
(単年度)
(単位:億円)
| 区分 | 10年度 (決算) |
11年度 (見込・ 補正後) |
12年度 (予定) |
| 保険料収入 一般会計より受入 日雇拠出金収入 運用収入 雑収入 計 |
60,524 8,980 7 89 205 69,805 |
59,490 9,135 7 25 146 68,803 |
63,645 9,421 6 25 149 73,246 |
| 保険給付費 医療給付費 現金給付費 老人保健拠出金 退職者給付拠出金 介護納付金 業務勘定へ繰入 諸支出金 予備費 計 |
43,187 37,892 5,295 20,769 4,215 - 1,562 38 - 69,771 |
42,429 37,065 5,364 23,544 4,793 - 1,521 43 400 72,730 |
42,930 37,607 5,323 22,008 5,109 3,943 1,500 48 400 75,938 |
差引過△不足額 |
(▲35) 34 |
▲3927 |
▲2692 |
| 事業運営安定資金(年度末) | 6,932 |
7,188 |
4,496 |
Data:社会保険旬報 2000.2.11 P16
平成10年度の政管健保の収支状況は、健保組合の解散に伴う財産継承を除外すると実質35億円の赤字で、6年連続の赤字となった。
平成11年度は、平成9年の健保法等改正の効果が一巡したこと、高齢者の薬剤一部負担の特例措置などを勘案し、当初予算では3057億円の赤字と見込んでいたが、不況の影響により被保険者数、保険料収入が予算以上に減少しており、現時点で赤字額は3927億円に膨らむ見込みだ。なお、平成11年度の第2次補正予算で、国庫負担繰り延べ分の一部が返還された結果、11年度末の事業安定資金の残高は7188億円になる見込みである。さらに、平成12年度については、介護保険制度の導入や医療保険制度の改正の影響を勘案し2692億円の赤字を見込んでいる。12年度末の事業安定資金の残高は4496億円となる見込みで、厳しい財政状況は今後も続くことが予想される。
平成9年に受益者負担を増やして収支のバランスを図ろうとしたものの、その効果はたった2年も続かなかった。赤字傾向が続くなら、政管健保の保険料率アップも予想される。
国民医療費を効率的な分配をしないと、結局はそのツケを国民が負担することになる。
全国公私病院連盟による平成11年6月分を対象とした「病院運営実態分析調査」の概要
調査対象:1185病院(自治体病院697、その他公的病院229、私的病院252、国立・大学付属病院7)のうち、赤字病院は808病院、68.6%。前年より4.3%改善。
表1)赤字病院の割合
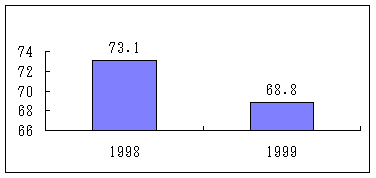
自治体病院が89.7%と9割近くが赤字となっているほか、その他44.5%、私的32.1%という状況である。100床当たりの医療費用対医業収益の割合(医業収支率)は104.9で、0.7ポイント改善している。医業費用に占める給与費の割合は51.5%(前年51.0%)、薬品費の割合は19.9%(前年20.8%)である。
表2)平均在院日数
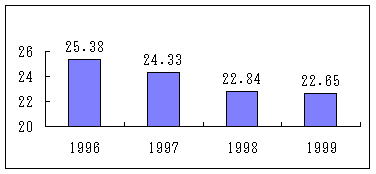
平均在院日数は年々短縮傾向にある。開設者別では、自治体病院22.83日、その他公的病院20.47日、私的病院25.94日で、平成2年と比べると自治体7.0日、その他公的6.6日、私的11.4日それぞれ短くなっている。
Data:社会保険旬報 No.2048 2000.2.1 P4
老年人口比率(総人口に占める65歳以上の高齢者の割合)が、平成9年に15.5%で、平成27年には、4人に1人が高齢者になると推計されている。その一方で、出生数は史上最低レベルの水準で、生産人口割合の低下は免れない状況である。現在の我が国の国民負担率(租税+社会保障費)は欧米諸国と比較すると、低い水準にあるが、高齢化の進行速度が速いので、人口構成の変化に合わせた社会保障制度を改変していく必要が生じたことにより、下記のごとく医療制度改革がとりくまれてきた。
日本医療制度の沿革は、大まかに4つの時代に分けて論じられる。
第1の拡張期は、戦後から1960年頃で、1)医療提供体制の骨格の整備(医療法、医師法等の資格制度)、2)病床の量的拡大、3)「公」中心、4)医療保険制度も国民皆保険計画で拡大路線であった。
第2の改善期は、1960年代から70年代で、1)医療提供体制の整備が量から質への転換(専門的診療機能、僻地医療、救急医療等)、2)民間医療機関の整備の助成、3)医療保険も給付内容・給付水準の改善がなされた。
第3の調整・改革期は80年代以降で、1)第1次医療法改正(地域医療計画の導入等)、2)第2次医療法改正(特定機能病院、療養型病床群の制度化等)、3)第3次医療法改正(有床診療所への療養型病床群設置、地域医療支援病院の制度の創設、広告規制緩和)、4)老人保健制度の創設、5)健康保険法の改正、6)介護保険制度の創設にとりくんだ。
第4の抜本改革期といわれるはずの2000年以降の抜本医療改革は、2002年以降に先送りされている。当初、厚生省は2000年度の実施を目指し、医療制度改革を検討しており、97年8月与党合意の「21世紀の国民医療」で医療改革の抜本改革案のたたき台を策定し、医療保険福祉審議会を発足させ、医療保険制度の抜本改革の4本柱である、高齢者医療、薬価、医療提供体制、診療報酬体系の見直しをうちだした。
健保組合、政府管掌保険の財政破綻により、抜本医療改革を望む声は大きいが、厚生省は、1月31日の医療保険福祉審議会の運営部会で、「改革は12年度から順次実施する」とする一方で、「検討に日時を要する事項については基本的に平成14年度からの実施をめざして検討を進める」とした。
医療保険制度抜本改革案は、下記のとおり。
* 薬価制度は、2000年度に薬価差益を縮小、今年10月を目処に中医協に薬価算定組織を新設し、薬価算定過程の透明化を図るほか、薬価差を解消するためR幅方式に代わる新たな薬価算定ルールを平成14年までに導入するとしている。
* 診療報酬体系は、2000年度から定額払いの拡大などの合理化を順次実施。
* 高齢者医療は、2000年度から老人医療の患者負担に定額の上限を設けた上で定率1割制を導入するほか、老人診療報酬の改定において、①高齢者入院医療の質の向上と効率化、②高齢者在宅医療の推進を図った。
2002年度をメドに新たな医療保険制度を検討(新制度導入は、2003年度以降)。
* 医療提供体制は、2000年度から広告規制の緩和、人員配置基準の見直しなどを順次実施。
日本版DRG/PPS(急性期入院医療の診断群別定額払い方式)の試行は1998年11月から全国10病院でスタートし、試行期間は5年間が予定されている。
対象は、一般の入院患者で、修正の診断群分類(13主要診断群・183分類)に該当するもの。15歳未満、転出、転入患者、治験の患者、検査入院患者は除外される。診断群分類の確定は、原則として患者の退院時に主治医が行う。
診療報酬の額は、診断群分類に応じた入院一件当たりの定額報酬(包括範囲は入院環境料、看護料、入院時医学管理料、検査料、画像診断料、投薬料、注射料、1000点未満の処置料。薬剤料と特定保険医療材料料も含む。加算部分は除く)に、現行の技術料部分の出来高報酬(指導管理料、手術料、麻酔料、放射線治療料、千点以上の処置料、リハビリ料等)と入院時食事療養費を組み合わせる形が基本となる。定額部分の報酬は、基礎償還点数(相対係数が1の場合の点数。3万8千8百3点)に、診断群分類に応じた相対係数(医療資源の投入比率。主要診断群5の循環器疾患のうち冠動脈バイパス移植術・心カテありが最大の9.28)をかけ、一定の調整・追加払いを行って算定する。
試行状況は、6ヶ月ごとにに報告されることとなっており、98年11月から99年4月までの半年間の算定状況が、99年10月13日の中医協で報告された。
それによると、試行対象10病院の全入院患者数に占める定額払い該当率は約3割である。定額報酬を該当率を病院別にみると、国立千葉病院が41.7%と最も高く、国立豊橋病院36.0%、国立埼玉病院30.8%と続く。
表1.試行開始後6ヶ月間の試行支払管理課方式算定の確定値(試行病院全体)
| 入院患者数 | 定額払い 該当患者数 | 該当率 | 対象病床数 (一般病棟) | |
| 千葉 | 2765 | 1154 | 41.7% | 467 |
| 豊橋 | 1174 | 423 | 36.0% | 327 |
| 埼玉 | 2044 | 629 | 30.8% | 400 |
| 南和歌山 | 1943 | 589 | 30.3% | 330 |
| 神戸 | 2214 | 629 | 28.4% | 304 |
| 九州 | 3853 | 1069 | 27.7% | 650 |
| 仙台 | 3525 | 970 | 27.5% | 668 |
| 岐阜 | 2278 | 596 | 26.2% | 250 |
| 諌早 | 2366 | 561 | 23.7% | 300 |
| 岡山 | 3336 | 726 | 21.8% | 661 |
| 合計 | 25498 | 7346 | 28.8% | 4357 |
試行後6ヶ月間の退院患者のみの平均在院日数は、試行前6ヶ月の17.7日から16.7日へと1.0日短縮した。このうち、DRG該当患者については、1.4日短縮(18.1日→17.4日)、DRG非該当患者でも16.4日から15.8日へとやや短縮している。
表2)診断群別平均在院日数の変化(概要)
| 件 数 | 平均在院日数(算術平均) | |||
| 試行前 | 試行後 | 試行前 | 試行後 | |
| 183診断群分類 に該当 |
9,938 (53.5%) |
9,823 (57.9%) |
18.8 |
17.4 |
| 183診断群分類 に非該当 |
8,638 (46.5%) |
7,128 (42.1%) |
16.4 |
15.8 |
| 総 数 | 18,576 | 16,951 | 17.7 | 16.7 |
表3)診断群別平均在院数の変化
| 分類 番号 |
診断群分類 | 合併症 | 診療行為等 | 平均在院日数 | ||
| 試行前 | 試行後 | 短縮日数 | ||||
| 204 | 白内障 | あり | 手術あり (両眼) |
22.8 | 15.5 | -7.3 |
| 631 | 鼠径ヘルニア | なし | 手術あり | 11.9 | 7.0 | -4.9 |
| 614 | 大腸の良性新生物 | なし | 手術あり | 8.5 | 5.6 | -2.9 |
| 509 | 狭心症 | 手術あり | 11.0 | 8.3 | -2.7 | |
| 203 | 白内障 | あり | 手術あり (片眼) |
11.1 | 8.4 | -2.7 |
| 1004 | 糖尿病 | なし | インシュリン注射あり | 30.2 | 27.7 | -2.5 |
| 1115 | 前立腺肥大 | なし | 20.5 | 18.9 | -1.6 | |
| 201 | 白内障 | なし | 手術あり (片眼) |
8.8 | 7.3 | -1.5 |
| 1006 | 糖尿病 | インシュリン注射なし | 23.1 | 21.9 | -1.2 | |
| 1205 | 子宮平滑筋腫 | なし | 手術あり | 19.2 | 18.1 | -1.1 |
*試行前調査は6ヶ月間のデータに調整した。試行後調査は、平成10年11月1日以後入院し、11年4月30日までに退院した患者データのうち、この10月5日現在で収集できたものに限る。
試行前後の病床利用率、入院外来比率、入院中死亡率はいずれも若干増加しているが、試行後の11月から4月は冬季をまたいでおり、その影響も含まれていると考えられる。
このほか、看護業務量や患者満足度・医療従事者満足度・業務改善などの調査は現在集計中で、まだ報告されていない。
中間報告で指摘されている問題点としては、症例数が半年で7346件で、単純計算でも年間1万5000例、5年間でも7万5000例のデータにしかならないことで、アメリカのDRGが1400万症例の膨大なデータから作成されたことに比べ、圧倒的な症例不足である点である。
また、効率的医療の実現をしていくためには、在院日数短縮という指標だけにとらわれず、クリティカルパスの導入と、これに必要な治療のガイドライン作りを行い、質の管理の方法論の確立が求められている。
Data:全日病ニュース 第488号 ‘99.11.15
社会保険旬報 No.2039 ‘99.11.1 P14,15
医療保険制度抜本改革の一環として、医療の質の向上と効率化を図るため、診療報酬体系の見直しを着実に進める内容になっている。医科、歯科、調剤別に、質的、量的双方の面における現行報酬の合理化・簡素化を図ることにより生じる0.9%の財源に、1.9%を加えた財源を、現時点で必要度の高いこれらの分野に重点的に配分された。
平成12年度診療報酬改定においては、「診療報酬体系(医科、歯科、調剤)のあり方に関する中間報告(平成11年12月1日)」に示された主要課題に従い、医療機関の機能分担と連携を促進する観点、医療技術を適正に評価する観点及び出来高払いと包括払いの最善の組み合わせを実現する観点から、基本診療料、手術料を中心に体系的な見直しに着手し、包括払いの範囲を拡大された。
また、平成12年度薬価制度改革にあわせて、薬剤使用の適正化策の拡大及び薬剤関連技術料の適正な評価を行う。さらに医療の質の向上と患者サービスの向上のため、小児医療の充実、回復期リハビリテーションの充実、逓減制の見直しを含む長期療養患者への必要な医療の確保、有効性・効率性の高い新規技術の保険導入、歯科医療技術の評価、患者への必要な情報提供の確保、在宅医療の充実等を評価する内容である。
今回の改訂では、200床以上の急性期をめざす病院と慢性期をめざす病院と機能分化を図るべく、ベッド床、紹介率、看護配置、正看比率、入院日数の指標によって、ホスピタルフィーの評価している。
画像診断については、質の向上と効率化を狙って、医療機器の共同利用の促進と新規機能についての評価がなされた。
改訂内容:
イ 既存のCT、MRI評価の見直し(引下げ)
| CT単純 | MRI単純 | |
| 頭部 | 665点 → 655点 | 1,680点 → 1,660点 |
| 躯幹 | 890点 → 880点 | 1,800点 → 1,780点 |
| 四肢 | 620点 → 610点 | 1,710点 → 1,690点 |
ロ 新規技術の評価
| CT特殊(新設) | MRI特殊(新設) | |
| 頭部 | 715点 | 1,760点 |
| 躯幹 | 960点 | 1,880点 |
| 四肢 | 670点 | 1,790点 |
(注)特殊CT撮影及び特殊MRI撮影
* 管腔(CTについては血管、MRIについては血管、膵胆管)描出を行った場合に限る。
* 特殊撮影を行うためのヘリカルCT装置、マルチスライスCT装置又は1.0テスラ以上のMRI装置のいずれかを有していること。
* 画像診断施設共同利用率は、100分の5以上であること。
改正案のポイントは、
① 新たな病床区分の法制化
② 適正な入院医療の確保
③ 広告規制の緩和
④ 臨床研修の必修化
今国会に改正法案を提出し、平成12年10月1日の施行を予定している。
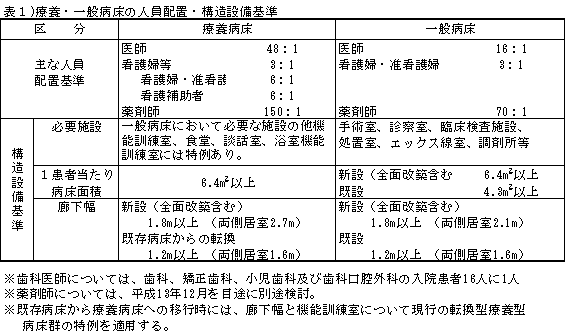
平成12年2月10日発健政第9号をもって諮問のあった「医療法等の一部を改正する法律案要綱(答申)」について、医療審議会として、医療を取り巻く環境の変化に対応するための課題に取り組むものとして了承した。ただし、一部の委員から、医療法上の人員基準は最低基準であり、一般病床の看護職員の配置基準は入院患者4人に一人とすべきとの意見があったことを付記する。
広告規制緩和のアイテムとして検討されている項目は、①中立的な医療機能評価機関が行う医療機能評価の結果、②医師の略歴・年齢・性別、③共同利用できる医療機器、④対応可能な言語、⑤予防接種(種別)、⑥健康診査の実施、⑦保健指導および健康相談の実施、⑧介護保険の実施に伴う事項(紹介をすることができる介護関連施設の名称等)の8項目が追加される予定。
Data:社会保険旬報 No.2051 2000.2.21
厚生省は1月19日に開かれた医療保険福祉審議会・運営部会に、昨年末の予算編成で決定した老人の自己負担見直しを柱とする健保制度等改正案要綱を諮問した。
改正案要綱の柱:
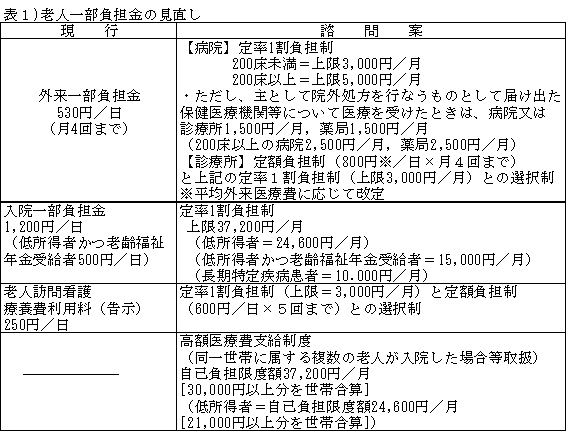
Data:社会保険旬報 No.2048 2000.2.1 P7
① 老人の患者負担い=老人の薬剤一部負担は廃止。入院は、定率一割負担、外来は病院は同じく定率一割負担。
② 高額療養費の自己負担限度額の引き上げ=一般は6万3600円プラス医療費から31万8000円を差し引いた額の1%、上位所得者(標準報酬月額56万円以上)は12万1800円プラス医療費から60万9000円を差し引いた額の1%。
③ 入院時食事療養費=760円を780円に引き上げる。
④ 一般保険料率と介護保険料率を別立てとする保険料率上限の見直し
⑤ 健康保険組合に対する指定制度の創設
上記について、平成12年7月実施が予定されている。